先々週の土曜日、所用で長崎に帰り、
友と飲み明かした翌日のこと。
友と飲み明かした翌日のこと。
それなら、ということで以前から気になっていた、中島川の河童さんたちを見に行ってきました。
まずは、本河内底部水源地の手前にある、水神神社のカッパ石から訪ねることにしました。
そして、川の左側を歩いていると立派な鳥居が見えてきます。

ここが水神神社です。
この大鳥居は、もともと諏訪神社の一ノ鳥居であったものです。
これも、寺町の「幣振り坂」の謂れとなった石材が使われているそうですよ。


水神神社は、もともと八幡町にあったものが大正9年に現在地へ遷宮されたそうです。
神社の裏手にまわると、川立神を祭った神殿があり、その手前に「かっぱ石」が据えてあります。
この石は、
「川立神の宿る霊石として、銭屋川(銭屋橋あたり)の一隅より社とともに移転したものである。
祭神は、兵統良神(ひょうすべらかみ)『俗に河太郎・河童』と称し、代々社側の川に棲み、
常に通って神様の守護・参詣者の守護を務めると伝わっている」
「川立神の宿る霊石として、銭屋川(銭屋橋あたり)の一隅より社とともに移転したものである。
祭神は、兵統良神(ひょうすべらかみ)『俗に河太郎・河童』と称し、代々社側の川に棲み、
常に通って神様の守護・参詣者の守護を務めると伝わっている」
このあたりに来るとわかりますが、その昔、河童が居たといってもおかしくない雰囲気が漂っている場所です。だからこそ、蛍の名所としても名高いところだったのだなあ、思いました。
参拝も済んで、中島川沿いに下っていきましょう。
国道34号線電車通りを横断すると

伊良林小学校に出ます。
それから、伊勢宮の手前あたりにくると



河童洞があり、雌河童と、ユーモラスなお顔の河童地蔵があります。
先の水神神社が八幡町にあったころ、神主に八匹の河童が家来として仕えていたという伝説に
なぞらえて、八天坊と名づけられています。
さらに下ると、現存する石橋の中で、私が一番すきな桃渓橋(ももたにはし)が架かっていますが、

この橋のスグそばに、小さな雌河童を火袋におさめた河童灯篭あります。

これは、中島川を守る会の方々が昭和51年に建立したそうです。

そして、一覧橋のたもとに

長崎の五僧に数えられる「慶西」が開祖である光栄寺が見えてきました。

その先の袋橋のちかくに、

最後のカッパ、「ぽんたくん」がいます。
説明板には
「上げ潮にのって迷子になり、中島川を上って来た子鯨をみつけて、
少年カッパのぽんたくん、背中に飛び乗り大喜び、昭和57年7月の大水害を
忘れぬためにも『ぽんたくん』をいつまでも可愛がってください」とあります。
これは、河童のマンガで有名な清水 崑の原作をもとにつくられた像です。
ちなみに、清水 崑は長崎生まれですよ。
ちなみに、清水 崑は長崎生まれですよ。
中島川は、その昔から長崎市民に愛された川でありますが、同時に
河童伝説も息づく、深淵な川でもあったのです。
その伝説を知る方々の尽力により、こうして河童の名所がいくつも建てられています。
皆さん方も、是非、時間があれば見に行ってやってくださいね!
河童伝説も息づく、深淵な川でもあったのです。
その伝説を知る方々の尽力により、こうして河童の名所がいくつも建てられています。
皆さん方も、是非、時間があれば見に行ってやってくださいね!
さあ、私はお腹がすいたので、


きっちんせいじの、トルコライスをいただいて帰ることにしますw
あ~~、おいしかった!
.
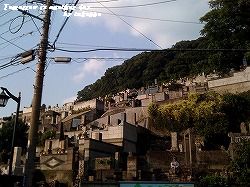

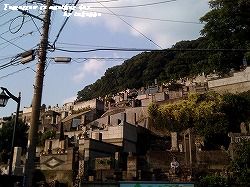







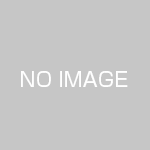


この記事へのコメントはありません。